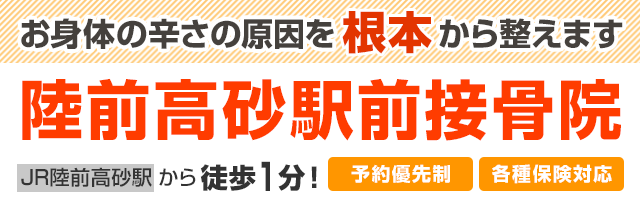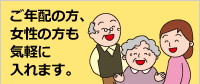巻き肩


こんなお悩みはありませんか?

肩こり・首こり
肩が前に巻き込まれることで、肩や首の筋肉に負担がかかり、慢性的なこりや痛みが生じやすくなります
猫背や姿勢の悪化
巻き肩になると背中が丸まりやすくなり、猫背や前傾姿勢になってしまいます。見た目の印象が悪くなるだけでなく、呼吸が浅くなったり、疲れやすくなったりすることもあります
頭痛やめまい
首や肩の筋肉が緊張し血流が悪くなることで、頭痛やめまいの原因になることがあります。特にデスクワークやスマホの使用時間が長い人に多く見られます
肩の可動域の制限
巻き肩の状態が続くと、肩甲骨や肩関節の動きが制限され、腕を上げにくくなったり、肩を回すと違和感を覚えたりすることがあります
バストの下垂やスタイルの崩れ
巻き肩によって胸が内側に押し込まれることで、バストが下がって見えたり、スタイルが悪く見えたりすることがあります。特に女性にとっては気になるポイントです
巻き肩について知っておくべきこと

1. 巻き肩とは?
巻き肩とは、肩が前方に巻き込まれた状態を指します。
デスクワークやスマートフォンの長時間使用など、前かがみの姿勢が続くことで起こりやすくなります。
2. 巻き肩のセルフチェック方法
ご自身で簡単に確認できる方法があります。
壁に背中をつけて立ちます(かかと・お尻・背中を壁につける)
このとき、肩が壁につかない、もしくは腕が前に出る場合は、巻き肩の可能性が高いと考えられます。
3. 巻き肩が引き起こす可能性のある不調
巻き肩は、以下のようなさまざまな不調の一因となる場合があります。
肩こり・首こり:肩まわりの筋肉が緊張しやすくなります
姿勢の悪化(猫背など):見た目の印象が悪くなり、疲れやすくなることがあります
頭痛やめまい:血流が悪化し、脳への酸素供給が減ることで起こる場合があります
呼吸の浅さ:胸郭が狭まり、呼吸がしづらくなることがあります
4. 巻き肩の原因
以下のような生活習慣や身体の状態が巻き肩の原因となることがあります。
長時間の前傾姿勢(デスクワーク・スマホ操作・車の運転など)
筋力のアンバランス(胸の筋肉の緊張と背中の筋力低下)
姿勢の悪さ(猫背やストレートネックなど)
腕を前に出す作業が多い(パソコン操作や料理など)
5. 巻き肩の軽減が期待できる方法
巻き肩は、日常生活の中で意識的にケアを行うことで軽減が期待できます。
ストレッチ:胸の筋肉を伸ばし、肩甲骨を寄せる動作を取り入れましょう
エクササイズ:肩甲骨を引き寄せる筋力トレーニング(例:背筋運動やローイング運動)
正しい姿勢を意識する:デスクワーク中に肩を開くよう心がけることが大切です
巻き肩は放置せず、早めにケアすることが大切です。日常生活の中で正しい姿勢を意識し、適度な運動やストレッチを取り入れることで、巻き肩の軽減が期待できます。
症状の現れ方は?

巻き肩によって見られる主な症状
肩の位置の変化
肩が前に出て、首が前方に突き出るような姿勢になります。
首や肩の痛み
肩甲骨周辺や首まわりに緊張を感じることがあります。
可動域の制限
腕を上げる、後ろに引くといった動作がしづらくなることがあります。
疲労感
長時間同じ姿勢を続けたり作業を行ったりすることで、肩や背中に疲労を感じやすくなることがあります。
施術のご提案
巻き肩の軽減を目的とした施術では、以下のような方法が用いられることがあります。
姿勢を整えるエクササイズ
正しい姿勢を保つためのストレッチや筋力強化の運動が有効とされています。
特に背中の筋肉を鍛えることで、肩の位置を整える助けになります。
マッサージや筋膜リリースなどの施術
肩や背中の筋肉の緊張を緩める施術を行うことで、肩まわりの血流が促進され、緊張感の軽減が期待できます。
その他の原因は?

巻き肩とは、肩が前方に巻き込まれたような状態のことで、以下のような症状が見られることがあります。
肩の位置の変化
肩が前に出て、首が前方に突き出るような姿勢になることがあります。
首や肩の痛み
肩甲骨まわりや首に緊張を感じることがあります。
可動域の制限
腕を上げたり、後ろに引いたりする動作が難しくなることがあります。
疲労感
長時間同じ姿勢を続けたり作業をしたりすることで、肩や背中の疲労感が強くなることがあります。
巻き肩の軽減を目的とした施術のご提案
巻き肩の軽減を目指す施術として、以下のような方法が挙げられます。
姿勢を整えるためのエクササイズ
正しい姿勢を保つために、ストレッチや筋力強化を行うことが有効とされています。
特に背中の筋肉を強化することで、肩の位置を安定させやすくなります。
マッサージやリリースを含む施術
肩や背中の筋肉の緊張を緩める施術を行うことで、肩まわりの血流が促進され、緊張感の軽減が期待できます。
巻き肩の原因と考えられる生活習慣
巻き肩は、以下のような要因によって引き起こされることがあります。
長時間の座り仕事
デスクワークや運転などで同じ姿勢を続けると、肩の筋肉が緊張しやすくなります。
筋力のアンバランス
背中や肩まわりの筋力が弱くなると、胸側の筋肉が過度に働き、肩の位置が前に傾きやすくなります。
運動不足
運動習慣がないと筋力や柔軟性が低下し、姿勢の保持が難しくなります。
ストレスや緊張
精神的なストレスにより筋肉が緊張し、肩の位置や姿勢に影響を与えることがあります。
日常の生活習慣
スマートフォンの操作や、足を組むなどの姿勢のクセが、無意識のうちに巻き肩を助長することがあります。
巻き肩を放置するとどうなる?

肩や首の痛み
巻き肩になると、肩や首まわりの筋肉が常に緊張した状態が続きます。そのため、肩こりや首の痛みが慢性的に感じられることがあります。
猫背や姿勢の悪化
巻き肩は猫背と密接に関連しており、不良姿勢がさらに進行する可能性があります。これにより全身のバランスが崩れ、身体全体に負担がかかりやすくなります。
呼吸が浅くなる
巻き肩により胸郭が圧迫されることで、肺が十分に拡張できなくなり、呼吸が浅くなる場合があります。これが疲れやすさや集中力の低下につながることもあります。
肩や腕の可動域の制限
肩関節の動きが制限され、腕を上げたり背中に手を回したりする動作が難しくなることがあります。
筋力バランスの崩れ
巻き肩では胸の筋肉(大胸筋など)が過度に緊張し、背中や肩甲骨まわりの筋肉が弱くなります。この筋力バランスの崩れがケガや筋肉の損傷の原因になる可能性があります。
見た目の印象の低下
姿勢が悪くなることで、他人からの印象が悪くなったり、自信が持ちにくくなることがあります。
当院の施術方法について

当院の姿勢矯正施術「TPC(トータルプロモーションチェンジ)」について
当院では、TPC(トータルプロモーションチェンジ)という姿勢矯正の施術を行っております。
こちらの施術は、約8割の患者様にご利用いただいており、当院の矯正施術の中でも特におすすめしている内容です。
腰痛や肩こりでお悩みの方も多くいらっしゃいますが、そうした症状の軽減が期待できる施術となっております。
具体的には、
骨盤のゆがみ
姿勢の不良
肩の可動域の制限
腰痛
巻き肩
などに対してアプローチいたします。
身体への負担を和らげ、痛みや不調の予防にもつながる施術です。
仕事や日常生活で身体に負担を感じている方も多く、その負担が症状につながっていることが多いため、その負担を抑えるための施術を丁寧に行っております。
どのようなお悩みでも対応できる内容となっており、多くの患者様におすすめしている施術です。
軽減していく上でのポイント

正しい姿勢を意識する
日常生活の中で、肩が前に出ないように姿勢を見直しましょう。
頭が前に出すぎていないか確認し、背筋を伸ばす習慣をつけることが大切です。
・胸の筋肉をほぐす
巻き肩の原因の一つは、胸の筋肉(大胸筋・小胸筋)の過度な緊張です。
以下の方法を実践しましょう。
- 壁やドア枠に手をついて胸を開くストレッチを行う。
- フォームローラーやマッサージボールを使って胸周りの筋膜リリースを行う。
・背中・肩甲骨周りを鍛える
背中や肩甲骨まわりの筋肉が弱いと巻き肩になりやすくなります。
次のトレーニングを取り入れると効果が期待できます。
- 肩甲骨リトラクション(肩甲骨を寄せる動き)
- フェイスプル(ゴムバンドやケーブルを使って肩甲骨を引き寄せる運動)
- ローイング(ダンベルやマシンを使った筋力トレーニング)
・デスクワーク環境を整える
- モニターの高さを目線の高さに調整する。
- 長時間座り続けないようにし、定期的に立ち上がって肩を動かす。
- 椅子の高さやキーボードの位置を正しく調整する。
・姿勢改善グッズを活用する
姿勢矯正ベルトやテープを一時的に使って正しい姿勢を意識するサポートをしましょう。
※ただし、使いすぎると筋力が弱まる可能性があるため注意が必要です。
・日常生活に意識を取り入れる
- 歩くときは胸を開き、肩甲骨を意識しましょう。
- 鞄は片側だけでなく、リュックなど両肩に負担が分散されるものを選ぶと良いです。
一貫して続けること
巻き肩の軽減には時間がかかるため、毎日少しずつ継続することが大切です。
朝や仕事の合間、就寝前などにストレッチを取り入れる習慣をつけましょう。
専門家に相談する
セルフケアだけでの軽減が難しい場合は、理学療法士や整体師、トレーナーに相談し、自分に合った方法を学ぶことをおすすめします。
監修

陸前高砂駅前接骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:茨城県牛久市
趣味・特技:スターバックスでソイラテを飲むこと、野球